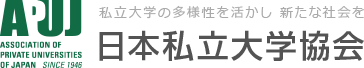アルカディア学報
大学の法的リスクに注意
今年4月の改正私学法施行までに相応の対策を
私立大学(本稿では学校法人の意も含むものとする。)に潜む法的なリスクは、学生との関係、教職員との関係、保護者との関係、役員との関係、取引業者との関係、所轄庁との関係、地域との関係など、枚挙にいとまがない。そのようなリスクが顕在化した際に、対応を誤って大炎上し、大きな痛手を及ぼす例もみられるところである。
おりしも、令和5年に私立学校法が改正され、令和7年4月に施行される。この中で、いわゆる「内部統制システム」という概念が現れ、その内容の一つとして、理事及び職員の「職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制」が定められた。いわゆるコンプライアンス体制である。大臣所轄学校法人等は改正法施行日から内部統制システムの体制整備義務を負うことになったため、各大学においては、今一度コンプライアンス体制を見直し、強化を図ることが不可欠な時機といえよう。
コンプライアンス体制の強化を図るためにまず何よりも重要なことは、法的リスクを適切に把握することである。それでは、大学においてどのような法的リスクがあるか。本稿では、大学特有の法的リスクが潜む学生と教職員に絞って紹介する。
1点目である学生に関する法的リスクについて、前提として、大学は学生と法的にどのような関係にあるかを考えてみると、大学は学生との間に在学契約を締結している。具体的には、学納金の支払いを受けることと引き換えに、教育サービスや施設利用の提供を行うとともに、学生の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っている。
学生の基本的な義務である学納金の支払義務との関係でのリスクという意味で一番典型的といえるリスクが、学納金の不払いリスクである。これについては、親権者等を連帯保証人に就任させる保証書を徴することが一般的によく行われているが、この保証について令和2年に施行された改正民法における個人根保証の規制が適用されることとなった。保証の上限額(極度額)を記載しないと保証書自体が無効になってしまうこととなったため、そのフォーマットにも注意が必要である。
また、教職員による学生へのハラスメントを大学が放置していた場合や学生が学内で事故に遭った場合など、学生が大学の中で事件・事故に巻き込まれたような場合には、大学は(施設の所有者としての責任を問われる場合もあるが)安全配慮義務に違反した責任を問われるリスクがある。学生がこのような事件・事故に巻き込まれることのないように、学生生活の環境を整えるような取組を行ったり、施設改修などを継続的に進める必要がある。
さらに、逆に学生が対外的に事件・事故を起こす場合も挙げられる。この場合、第一次的には学生本人が法的責任を負うことになり、必ずしも直ちに大学が責任を負うことにはならない場面が多いものと思われるが、当該事件・事故の報道が過熱し、在学している大学の情報とセットで報道された場合などには、大学として大きなレピュテーションの低下につながるおそれがあるので、適切な広報対応が求められることとなる。
2点目である教職員に関する法的リスクについて、前提として、大学は教職員と法的にどのような関係にあるかというと、大学は教職員との間に労働(雇用)契約を締結している。具体的には、労務の提供を受けることと引き換えに賃金を支払うとともに、教職員の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っている。
まず、教職員に関するリスクで典型的なものとしては、労働条件、特に労働時間に関する規制への抵触リスクが挙げられる。教職員には労働基準法が適用され、労働時間が法定されており、それを超過する場合には、(いわゆる36協定を締結していることを前提に)残業代を支払う必要があり、超過時間が相当多い場合には労働が禁止されることとなっている。特に、教員の勤務時間については従前よりあまり適切に管理されてこなかったこともあり、想定外の残業代不払いリスクが眠っている可能性がある。今一度労働時間管理の手法の見直し・改善を図る必要があろう。他にも、昨今、法改正によりいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との同一労働同一賃金の原則が採用されることとなったため、その観点での労働条件の見直しも検討する必要がある。
また、教職員による業務上の不正行為や過失行為も挙げられる。不正行為とは、横領や背任などはもちろん、研究不正や研究費不正、ハラスメント、名誉毀損など多岐にわたる。過失行為についても、個人情報漏洩、安全保障貿易管理に関する規制違反など、こちらも多岐にわたっている。研究不正や研究費不正については、ガイドラインが出ており、一定の対策がイメージしやすいところであるが、様々な不正行為や過失行為を想定した対策が望まれる。
加えて、雇用契約を締結している教職員に適用されるものではないが、近接した事柄として、個人に役務提供を委託する場合などに適用される、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が制定され、令和6年11月1日に施行された。該当する場合には、取引条件の明示、支払期日の設定・支払義務、遵守事項など取引の適正化に関する規定が適用されるとともに、募集情報の的確な表示、妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解約等の事前予告・理由開示など就業環境の整備に関する規定が適用されることとなる。典型的には学校医や産業医、カウンセラーやアドバイザーなどが対象となる可能性があり、それらの者との契約内容や運用が同法違反となっているリスクがある。このあたりも、未対応であれば速やかに見直し・改善が必要となる。
このような学生や教職員に関する(故意の)不正行為や過失行為を防ぐにはどうすればよいか。ここでは、発覚した際により影響の大きい不正行為に絞って整理すると、観点は大きく2つある。1つには不正行為ができる限り起きない仕組みを構築すること、もう1つには不正行為を起こさない風土をつくることである。
1つ目の仕組みについては、まずは各教職員の役割・権限・レポートラインなどを規程等で明確化することが重要である。誰にどのような権限・職務・役割があるのかが明確でないと、権限が曖昧になり、本来権限のない者の行為が好き勝手に行われたり、監視・監督が効かなくなるおそれがある。また、平時・有事それぞれについて、対策を整理するとともに、コンプライアンス・マニュアルを作成して現場に配布することも有用であろう。加えて、実際の運用面でも、経理不正が起きにくいソフトウェアを導入したり、ダブルチェックを実施するといったことも考えられる。さらに、内部通報制度の整備も肝要である。消費者庁が指針を示しており、それに則った体制整備が基本となるが、通報の匿名性を確保して実を上げるために法律事務所など外部に通報窓口を設置する大学も増えている。
2つ目の風土については、やはりまずは大学としての行動憲章・行動指針を策定するとともに、不正を絶対に許さないというトップのメッセージを定期的に伝えることが重要である。加えて、コンプライアンスに関する研修の機会を設けることも肝要である。特に、研修については、定期的に実施することが大切である。
大学には様々な法的リスクがある。それらを拾い落とすことなく集約し、平時と有事それぞれの対策を検討し、取組を進めておくことが、令和7年4月の改正私立学校法施行を控えたこの時期において大変重要である。