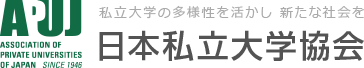アルカディア学報
修学支援新制度の奇妙な拡充
新制度の創設と目的のねじれ
高等教育の修学支援新制度が2020年度に発足してから4年が経った。この制度は、当初の想定では、予算規模で最高年額約7600億円という、これまでの日本の高等教育の歴史の中でも画期的なものであった。文部科学省の推計によれば、「制度開始前(平成30年度)には約40%と試算された住民税非課税世帯に属する者の大学等進学率は、令和5年度では約69%」と、高等教育機会の向上に効果があるとされている。
しかし、この制度にはその目的自体にも制度自体にも問題が多い。このことを筆者はさまざまな機会に指摘してきた(「いわゆる『高等教育の無償化』のわかりにくさ」『IDE 現代の高等教育』661など)。目的に関しては、この新制度を規定する「大学等における修学の支援に関する法律」の目的は「第1条(前略)子どもを安心して、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。」と、少子化対策である。学生支援の最重要な目的である教育機会の均等は目的となっていない。これは、「税と社会保障の一体改革」のため、社会保障にしか使えない消費税値上げ分を財源としていることによる。つまり、新制度は当初から、目的がねじれていたのである。しかし、低所得層への学生支援が少子化の改善につながるというロジックははなはだ疑わしい。
制度上の問題点
また、その制度についても、急拵えのため、多くの問題点を含んでいる。このことは、法案の国会審議でも問題となり、附則第3条に「政府は、この法律の施行後四年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。」と見直しの規定が制定された。
しかし、これまでのところ、実際の見直しは「機関要件の厳格化」(2022年)と「成績要件の厳格化」および、多子世帯や中間層などへの支援の拡充(2024年)にとどまっている。
筆者が最大の問題だと考えているのは、支給基準(世帯年収による)が3段階しかないため、いわゆる崖効果(反対側から見れば壁)が生じることである。年収が1円でも異なれば、支給区分が異なり、最高約50万円もの差が生じるという問題である。実際、多くの大学で、年収が増減したため、支給区分が異なったり、支給対象から外れたりという問題が生じている(詳しくは、『高等教育の修学支援新制度と私立大学』私学高等教育研究所2023年を参照されたい)。
新制度の拡充では、中間層(世帯年収600万円程度まで)の支援対象に多子世帯と私立理工農系が加えられた。多子世帯では従来の制度と同様、授業料減免と給付型奨学金の2本建であるが、私立理工農系は給付型奨学金の対象にはならない。これは子供未来戦略会議の提言(2023年)では、両者とも給付型と授業料減免が含まれていたこととは異なっている。
しかし、現在では多子世帯は世帯年収にかかわらず、支援の対象となっている。だが、これも授業料減免のみで給付型奨学金は対象とされていない。その理由も明らかではない。このように、支援対象によって減免か給付型奨学金かも異なり、統一したロジックでの拡充ではない。このためもともとわかりにくい制度がさらに奇妙に複雑でわかりにくい制度となっている。
機関要件の厳格化
機関要件では、従来、3つの条件のすべてにあてはまった場合のみ、支援対象機関(確認大学等)を取り消された。これに対して、さらに、機関要件が厳格化され、3つの条件のうち「直近3年度全ての『収容定員充足率』が8割未満但し、直近の『収容定員充足率』が5割未満に該当しない場合であって直近の進学・就職率が9割を超える場合、確認取消を猶予」とされた。在り方検討会議の資料(2022年)によると令和4年度には確認取り消しにあてはまる高等教育機関は15校(うち大学・短大は4校)だったが、この機関要件の厳格化により、118校になるとされている。
実際、昨年9月の段階で、高等教育機関の確認取り消しは70校でうち大学・短大で確認取り消しは35校、専門学校34校で、高専でも初めて取り消しが1校出ている。70校は少なくないし、今後さらに増えると思われる。
学生を保護し、赤字大学の救済にならないためとも言われる機関要件の厳格化。なかでも定員未充足が高等教育機関にどのような影響を与えるかは大きな問題だ。しかし、定員未充足即赤字大学ということでは必ずしもない。また、必ずしも大学の質が低いわけでもない。地方の大学や人気のない大学や専門、これは例えば福祉や介護に多い。しかし、これらは人気がなくても社会にとって非常に重要なはずだ。だが、学生が集まらないから定員未充足になっている。こうした大学の学生は定員未充足というだけで新制度の対象とならない。つまり赤字大学と定員未充足大学と質の低い大学を同一視していることが誤りであり、赤字大学の救済にならないために定員未充足を機関要件にすることが問題なのだ。
さらに、高等教育機関に全国一律の基準を設けていることも大きな問題である。専門と同様、地方によって実情は大きく異なる。他方、一律でない基準や部分的な拡充は制度を複雑化し、ますますわかりにくくする。全国一律ではない基準を設けることや選択肢を増やすことと、制度の複雑性によるわかりにくさは両立し難く、難しい問題である。この対策として、正しい情報の周知が大きな課題となっている。
学業要件の厳格化
学業要件については、高等教育の修学支援新制度の在り方会議が昨年6月に報告を出した。その主な内容は機関要件と同じように、学業要件の厳格化であった。出席率や取得単位数が引き上げられた。
しかし、学業要件のうちでも、成績下位4分の1が連続した場合の支援廃止については、停止とした他、ほとんど変更されていない。この要件は、相対評価のため、学生本人の努力だけでは如何ともし難いという問題がある。また、優秀な学生が多い大学ほど相対評価では厳しさを増す。在り方会議では、こうした相対評価の問題点は検討されているものの一律の絶対的・統一的評価は不可能とした。また、「制度の頻繁な変更は学生等や学校関係者の混乱を招くおそれがある」ことも理由としている。その恐れがあることは否定しない(先にふれたように既に多くの混乱が生じている)が、附則の制度改正の必要性をどのように考えているのだろうか 。
筆者は新制度の問題点をただ批判したいのではない。日本の学生支援の歴史の中でも、画期的な、巨費を投じる制度だけに、少しでも改善されるために、指摘しておきたい。それは附則の趣旨でもある。