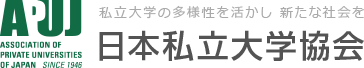特集・連載
私大の力
<47> 地方創生「核」を担うには
「在り方」改革
答申へ最終論議
■「大学はがんばる!」意気込む特別部会
国民の関心、とくに、地方の人たちの反響はどうだろうか。
中央教育審議会の「高等教育の在り方に関する特別部会」がまとめた答申案に対するパブリックコメント(意見募集)が昨年末から実施され、15日締め切られた。
各地の大学をどう再編するか。答申案では「縮小」と「撤退」がキーワードとされ、地方の私立大学にとっては、いよいよ目の離せない最終審議に入る。
「重視すべき観点」に、高等教育機関が「核」となっての地方創生の推進を掲げた。東京一極集中の是正、災害や感染症などに強い国土形成のためには、大学が地域社会の持続的な発展を牽引(けんいん)することの重要性を強調している。
「核」という文字を入れることに、特別部会を率いる大学分科会長、永田恭介(筑波大学長)はこだわった。
委員から「大学は人材育成の役割を担うが、地方創生の『核』はあくまで産業界ではないか」という意見が出ると、永田は「それを大学中心に持っていこうという我々の矜持(きょうじ)として書いている。大学はがんばる、ということ」と応じていた。
現状のままでは、日本の「国力」は低下するばかりだ。地域の「知の拠点」である大学がしっかりしなければならない。その危機感が、少子化のなかでも国民の「知の総和」を高めるとする文言になったが、具体的にはどうするか。その肝として、地方創生という国の政策に積極的に関わっていくことに集約されつつある。
政府は「地方創生2・0」を看板に掲げ、「地域の『産官学』に金融、労働、報道を加えた『産官学金労言』が一体となり、特色ある発展を目指すところを後押しする」という。首相の石破茂は10年前、初代の地方創生担当相を務め、成果が不十分だった反省から「新たな取り組みを進める。今度失敗すると大変なことに」と力説する。
この政府方針にどう応じるかが、大学にとって重要な課題となってきた。
答申案では、とくに国立大学に「公私立大や地方自治体などの連携」の牽引役を求めた。筑波大学長をつとめる永田の部会長としての「矜持」を示す文言だったのだろう。
もちろん私立大学も連携への努力に全面協力すべきだが、問題は、部会でも議論になった国公私立間の格差、とくに財政面で「同じ土俵」に立たされておらず、国費の投入額は国立と私立で学生1人当たり13倍という差がある現実である。
教育国債や自治体の交付金、企業からの寄付といった財政支援も検討されるが、それをどう国の政策に反映し、私立大が「地域連携」の一翼を担える環境を整えるかだろう。
パブリックコメントを経て最終のまとめに入る特別部会の論議が注目される。
■自治体の「当事者意識の希薄さ」も課題
答申案では、地域連携にとくに重要な役割を果たすべき地方自治体の「当事者意識の希薄さ」も指摘された。「大学行政は国の役割という意識が強く、担当部署も十分には整っていない」という。
昨年、特別部会に示された「アンケート調査」によると、都道府県・政令指定都市の9割が「域内の高等教育機関との連携を担当する部署がある」と回答している。
しかし「担当」とされても、連携の業務の割合は2割程度という回答が最も多く、平均では4割に届かない。つまり、大学などとの連携を「主たる業務」とする部署の設置は限られている。
「地域連携プラットフォーム」も3分の2が参加しているが、「プラットフォームの活動がめざすべき水準に達しているかといえば、道半ばと感じる。大学・自治体の双方がビジョンをしっかり共有しておかなければ、形だけの連携になりかねない」(文部科学省の担当者)というのが現状だ。
大学が地方創生の「核」となるためには、まずは地方自治体との連携が欠かせない。答申案まとめの議論では重要なポイントになる。
特別部会には、連携の先進地として山梨県の山梨大学長、中村和彦が委員として参加している。国立の山梨大(甲府市)と山梨県立大(同)が立ち上げた一般社団法人が令和3年、国公私立の枠を超えて協力する「大学等連携推進法人」の第1号として文科省から認定を受けている。
中村によると、両大学では学生が受講して単位を取れる「連携開設科目」の設置を進め、今年度は教養科目を中心に187科目に拡大している。「山梨県は東京にも近く、若者の流出が目立つ」として、私立大学にも参加を呼びかけているという。
先のアンケートによると、地域連携の課題として「経済的な修学支援の不足(自治体からの奨学金など)」「自治体に関する情報不足(連携窓口が分からない、意向が分からない)」などが挙げられた。
大学・自治体に共通するのは「連携の中心となる専門家やコーディネーターが見つからない」という問題だった。
文科省の担当者は「コーディネーターに条件はないが、重要なのは幅広い視点を持って、全体を調和させながら議論をまとめられるかどうか。連携が進む地域の実務担当者や大学の学長、行政や金融を含む産業界など、さまざまな人材が考えられる」としている。
■「責任あるコーディネーター」が必要に
「地方創生に結びつく地域連携では責任あるコーディネーター、そして各機関の担当者の当事者意識が重要である」。答申案は、そう強調する。
政府はこの観点から、自治体の雇用改善に着手するという。具体的には、非正規の「会計年度任用職員」の制度を見直し、地方公務員の副業・兼業の弾力化などを進める。
総務省の調査によると、会計年度任用職員は全国に約66万人おり、このうち76%を女性が占める。年度ごとの契約で雇用が不安定なうえ、正規職員に比べて賃金が安く、ときに「官製ワーキングプア」などと呼ばれる。
地方創生の有識者会議でも「正規化をはじめ雇用の安定こそが必要だ」との意見が出ている。とくに若者や女性たちが安定した立場で継続的に自分の職務を遂行できるようにすることは、地域連携プラットフォームのような組織を運営するための「当事者意識」を高めるうえでも重要になる。
「自治体予算との兼ね合い」はあるが、地方創生が言われて10年を経ても東京一極集中を食い止められないのは、「若者や女性に魅力的な地方をつくる有効策が打ち出せなかったことが要因」と指摘される。
昨年4月、この10年を総括した元日本創成会議座長(現・日本郵政社長)、増田寛也は「少子化基調は変わっていない」とし、重要な反省点として「地方創生の部署の看板がたびたび書き換えられ、自治体や政府では3年くらいで担当メンバーが交代するため、政策の狙いや責任の所在があいまいになってしまった」と訴えていた。
担当者の当事者意識は、地方創生の「核」を目指す大学側も考えるべき課題だろう。
■地方の大学の「体力」維持が重要課題だ
「地域連携」が各地で始まっていることはアンケート調査でも明らかだが、それを新たなステージに引き上げるには大学の「縮小」と「撤退」も不可避、というのが中教審の答申案である。私立大学にとっては直接、経営問題に関わってくるだけに、極めて厳しい選択を迫られるところも出てくる。
本紙元日付の「新春座談会」でも懸念する意見が表明された。
日本私立大学協会長、小原芳明(玉川大学理事長・学園長)は「ある大学が『定員を縮小する』といった場合、週刊誌などではあたかも撤退を前提としているような記事になってしまう。それが風評被害へとつながる。縮小と撤退は完全に分けて考えないと、文科省の政策に応じる大学は少ないでしょう」と述べた。
これを受け、特別部会の副部会長でもある大森昭生(共愛学園前橋国際大学長)は「(答申案では)『適正規模』という表現をしてはいますが、実際は『縮小化』なんですよね。そして規模を縮小すると、(特に地方では)アクセスの問題が出てくるというように、規模とアクセスは時にトレードオフの関係になっています。そこをどうしていくのかが、最大のポイントになるのかなと」と応じている。
アクセスとは、地方の若者にとっては自分の住む地域に大学がないことが、人口流出につながる要因になるということである。
地域とのアクセスを確保して、その特色に応じた人材育成を果たすのが地方の大学に課された役割である。大学を地方創生の「核」にするためには、そのことを前提に考えなければならない。
地域連携で必要となるのは、大学が経営面でもしっかりとした「体力」を維持すること、そして地域のニーズに応じられるよう「教育の質」を高めることである。
地方の、とくに、しっかりとした私立大学への国の支援強化が求められる所以だ。