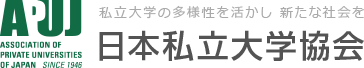特集・連載
私大の力
<48> 答申内容の具体化へ
助成50年の節目に
「私立中心」の政策実現を
■「もともと私学の国」の歴史を背負って
今年は1975(昭和50)年の私立学校振興助成法(私学助成法)制定から50年になった。昭和100年、そのちょうど半分の半世紀が過ぎたことになる。
第4条には「国は、大学などを設置する学校法人に対し、教育または研究に係る経常的経費について、その2分の1以内を補助することができる」と謳っていた。
補助率は、数年後に約3割(29・5%)に達したものの、これをピークに低下の一途をたどり、私学側と政府とのせめぎ合いがつづいてきた。直近では8・9%にまで減少している。
私立大の数が当時の307校から624校(昨年)へと増え、国の財政負担が大きくなっている事情はあるものの、「2分の1」という目標から大きくかけ離れた現状に私学関係者は苦い思いをしている。
今回、中央教育審議会大学分科会は「高等教育の在り方に関する特別部会」での15回におよぶ議論を「我が国の『知の総和』向上の未来像~高等教育システムの再構築~」にまとめ、文部科学大臣に答申した。
昨年春、その審議のなかで大きな反響を呼ぶ発言があった。
慶應義塾塾長、伊藤公平が「国立大の学生の年間負担(学納金)を、平均で私立大並みの150万円程度に設定すべきだ」と提起した。そのことが国公私立大の「共通の土壌」を整備することにつながり、「大学生の8割近くが通う私立大・短大は、公平な環境で建学の精神に基づく経営努力に取り組むことができる」と。
「よく言ってくれた」、と溜飲が下がる思いで聞いた私学人は少なくない。
「もともと日本は私学の国だった」とは教育学者、天野郁夫の言だが、江戸時代の教育は私塾すなわち私立学校が主役だった。慶應義塾は、明治政府が1871(明治4)年に文部省(現・文部科学省)を設ける前に福澤諭吉によって創立されている。
それが明治の文教政策によって、官立(国立)優先・官尊民卑へと転換された。帝国大学を頂点にした国立の覇権が確立するのを目撃したのが慶應の人たちだった。
伊藤の今回の「共通の土壌」発言は、この歴史を背負った発言と見ることもできる。さらに言えば、「もしも明治政府が国立ではなく、私学を育成する方針を選んでいたら、少なくとも現在のように国立・私立の待遇格差に煩悶する事態にはならなかった」と考える私学人は少なくないだろう。
今回の答申は「18 歳人口が急激に減少する時期まで10年しかない」として、「大学全体を適正な規模に縮小・再編しながら、教育の質向上や機会均等を実現させていく」というものだ。
そのうえで国に対して、「2040年までに大学の学部進学者が約 27%減少することを踏まえ、今後10 年程度に取り組むべき政策パッケージを策定し、本答申に記載した具体的方策の実行に速やかに着手することを求める」とした。
新年度から始まる立案作業のなかで、大学への公財政支援、ことに国公立と私立の格差是正にどのような対応がとられるか注視していくべきだ。
■「知の総和」向上は地方大学の死活如何に
とは言っても、慶應塾長の発言は、いわゆる私学の雄、東京にある資金豊富な大学の意見表明であり、地方の中小規模大学とでは緊急に解決すべき課題も異なる。同じ私立大のなかでも立ち位置が違うことは認識しなければならない。
あの発言が「国立と私立の待遇格差」を象徴的に社会に知らしめた意義は大きい。しかし、今回の「知の総和」答申の肝は、高等教育機関の東京への一極集中の問題、さらには、私学のなかでも大規模大学と地方の中小大学の置かれた環境の違いに配慮した政策をどう具体化するかという点にあった。
特別部会長の永田恭介(筑波大学長)が繰り返したように、深刻なのは少子化に伴う日本の国力低下であり、大学全体の底上げを目指す改革によって国力向上をどう図るかに議論の焦点があった。
大学教育の質、規模、アクセスという3本の柱をめぐって、慶應のような恵まれた歴史ある大学のそれではなく、より深刻な事情を抱える地方(地域)の大学をどう元気づけるかということにならざるを得なかった。
その課題は、「各高等教育機関の執行部や教職員はもとより、進学希望者や学生、その保護者、地域社会、産業界など様々なステークホルダー」がこぞって考えなければならないという表現に集約されている。
文科省が「地域大学振興室」を新設するのは、地方・地域の懸案をまず打開しない限り、日本の高等教育の将来が危うくなるという答申の危機感を受けたものである。
たとえばアクセス問題では、先日実施された大学入学共通テストで、愛媛、佐賀、熊本の3県の試験会場は県庁所在地にしかなかったという。
愛媛県は松山市内の大学3か所だけで、「遠方の受験生に不利になる環境を改善してほしい」という声を受けて、他の市などから会場新設の要望が出ていたものの、大学側からは「困難」との回答があったと、朝日新聞は報じている。
地方の若者が地元の高等教育機関から遠ざかっていく、というアクセスの問題は全国的に深刻化し、それが地方からの人口流出の原因にもなっている。
戦後の日本は、私立大が地域間をつなぐ血管のように増えたことで、国を発展させる礎となった。日本私立大学連盟も昨年8月、「私立大がどれだけ質の向上を図れるかが、国民全体の能力の総和(筆者注・「知の総和」)の増減に大きく関わる」との意見表明をしている。
■進学者増の対応は「私大頼り」という現実
日本私立大学協会の私学高等教育研究所主幹、西井泰彦によると、私学助成法が成立した1975年度の入学定員充足率(入学者数を定員で割った数)は最高の184%だった。このとき、大都市の私立大や短大では校地の確保も追いつかないほどで、収容学生を思うように増やせなかったり、定員の10倍を超える学生を受け入れたりする大学も見られたという。
その大学入学者数は今年度、募集定員の総計を1万人以上も下回って定員充足率も98%と初めて100%を切り、本格的な「大学全入時代」に突入した。
この結果、「難関大では受験競争が残る一方、入学希望者が募集定員に達せず入試が機能しない大学との二極化」(教育ジャーナリスト、石原賢一)が進み、教育の「質」を維持するうえでも、今回答申の言う危機が迫っているとの指摘もある。
西井によると、50年前に私学助成の法的根拠が確立して経常費補助が拡充されたのに伴い、入学定員は届出制から認可制になった。その後、定員超過率は連続して低下する時期があったが、1992(平成4)年度をピークとする18歳人口の戦後2度目の急増期には、臨時的な定員増が認められ、やがて、その恒常定員化などが進められた。
このように私立大は、18歳人口の増減という起伏に対応する国の政策のなかで、いわば安全弁のような役割を常に担わされたのである。国立大の数を変えないまま、進学者の受け入れを「私大頼り」にしてきた行政側の責任も大きいと言わざるを得ない。
■国立大「大学院中心の再編」で住み分けも
私大協会長の小原芳明(玉川大学理事長・学長)は特別部会のヒアリングで、歴史的経緯を踏まえて、「私立大を中核とした高等教育のグランドデザイン再構築」を改めて求め、国立大は「大学院を中心に再編する」というパラダイムシフト(構造的大転換)を推進するよう訴えた。
これは「もともと日本が私学の国だった」という原点を意識した提案であり、明治以降に国立優先の国策が推進されるなかでも、国民の中間層の育成に私学が果たした実績を改めて考えてほしいという要求でもあるだろう。
高等教育全体の縮小が避けられないなかで、国公私立の各大学の役割分担を考えたとき、国立大は学部定員を縮小し、大学院での世界トップレベルの研究や国立でなければ困難な教育・研究に特化すべきだ、という提案は現実的なものと言える。
一方、私立大には、学部教育においてさらなる「質」の向上をはかり、地域の知の拠点として、その活性化に寄与する努力を求めていくべきである。
国の私学政策は、ときどきの財政事情はあったにしても、その枠組みも明確な形で形成されないまま、大学の大衆化、規制緩和に伴う市場主義に突き進んでしまった、と指摘する専門家は少なくない。
今後の政策パッケージの具体化に向けては、全国のバランスある成長を見据えた高等教育の全体像を描きながら、各地域の特色を損なわない施策が実現できるよう、個々の大学と大学団体、行政の3者の緊密な連携が求められる。